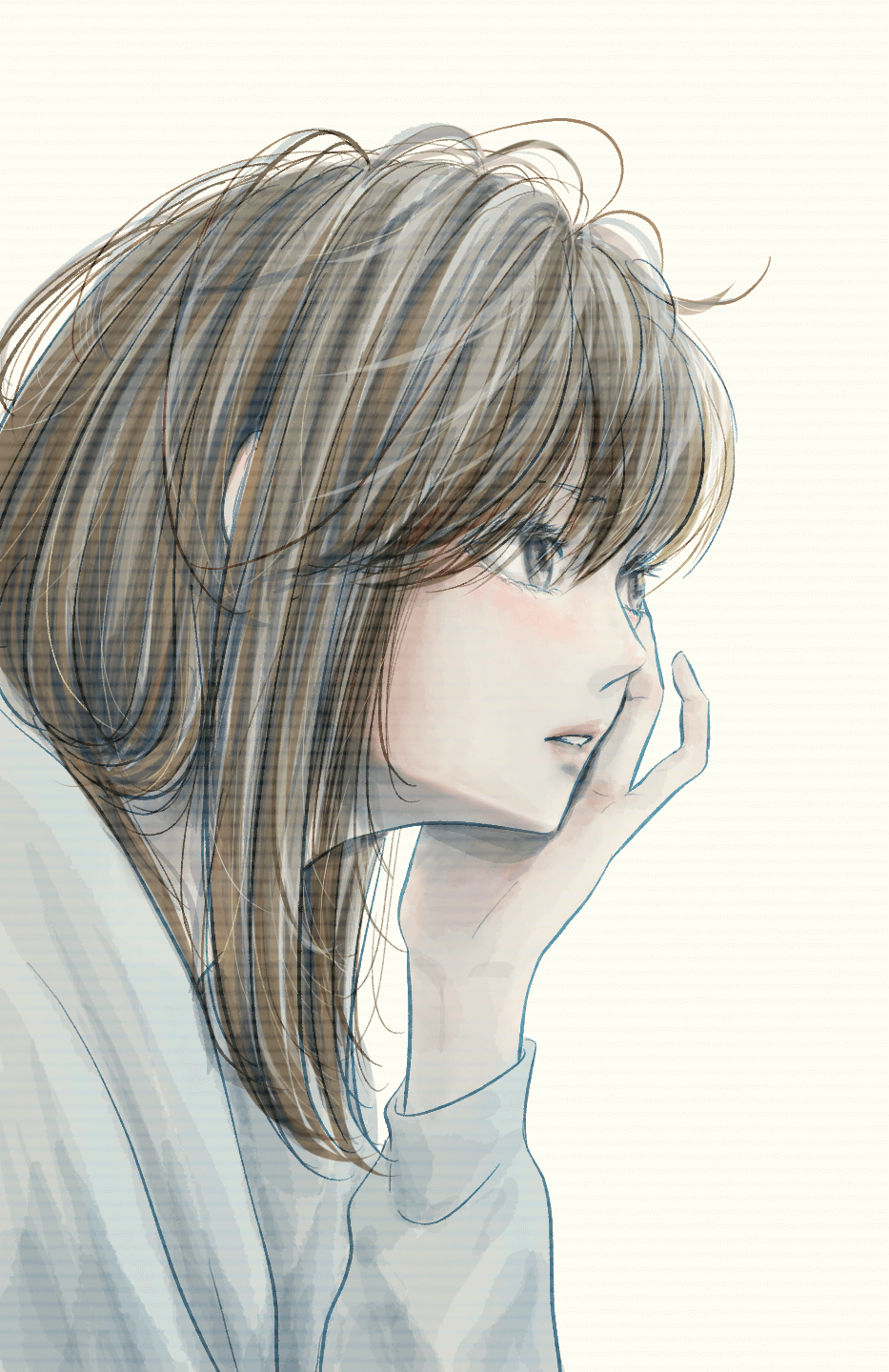夫の浮気の兆し
小さな街、北海道では、最近の暖かさで桜が満開になった。私の家の隣には公園があり、その中に大きな桜の木がある。リビングからは、その桜の花びらが春の風に舞っているのが見える。
ある日曜日の早朝、夫の俊太郎に「お願いだから行かないで」と懇願した。心の中の不安から逃れたくて、わがままを言ってしまった。夫と離れることが怖かったからだ。しかし、彼は振り返ることもなく、鏡を見つめながらシェービングクリームを拭い去っていた。私の声は届いていないようだった。
彼は身支度を整えると、視線も合わせずに車に乗り込み、愛用のゴルフバッグを持って出て行った。その玄関には、知らない香水の強い香りだけが残っていた。数ヶ月前から、洗面所の引き出しには見慣れない香水が隠されていた。大学時代からの24年間、香水が嫌いだと言っていた夫なのに。
冷たい玄関ドアの前に立ち尽くし、私の目からは涙が止めどなく流れ落ちた。
今から24年前、夫は大学の写真サークルの二つ上の先輩で、私が入学した年の春に新入生歓迎会で隣に座ったのが最初の出会いだった。駅前の安居酒屋で、自己紹介が終わった後、皆が騒ぎ始める中、彼は静かに距離を置いている姿が印象的だった。私が我慢できずに話しかけると、映画の趣味が合うことがわかり、少し距離が縮まった。
その後、彼は時折レンタルショップで面白そうな映画を借りてきて、私に声をかけてくれるようになった。「良かったら一緒に観ない?」と誘われ、私は嬉しく思った。最初は彼のアパートに行くのに戸惑ったが、彼の真面目で奥手な態度に安心した。サークルでは無口だった彼が、映画の話をすると饒舌になる姿が特別で、信頼されている気がして嬉しかった。
一年をかけて私たちは特別な関係になり、彼は私にとって初めての男性、私は彼にとって初めての女性だった。彼が先に大学を卒業した後、私たちは遠距離恋愛を経て、私の卒業を待って結婚し、この小さな北海道の街に住むことになった。彼は義父の設計事務所で建築士として働き、私は事務員として働き始めた。
20年が経ち、三人の子どもを授かり、平凡だが穏やかな生活を送ってきた。今年、長男の悠人は高校2年生、長女の美穂は中学2年生、次男の健二は小学6年生だ。そんな我が家に、小さな変化が訪れたのは約半年ほど前のことだった。それは初めは見落としてしまいそうな、とても小さな出来事だった。
「ねえ、俊太郎さんちゃんと聞いてる?」 私はダイニングテーブルで夕食を食べる夫の顔を覗き込んだ。 「ん?え?なんだっけ」 「今ずっと説明してたでしょ。悠人の進路の三者面談。来週の月曜日の4時から。いつも学校に行くの私ばかりだからたまには俊太郎さんに行って欲しいの。悠人の大学進学の大事な話だから」
「ん?ああ、わかった、わかった。時間空けておくよ」 「お願いね。忘れないでね」 「大丈夫だってば」 「ほんとかなぁ」 悠人は建築士になるべく四大の建築学部を目指していた。 それは義父母とそして夫の希望でもあった。 口にこそ出さないが夫は将来設計事務所を悠人が継いでくれることを望んでいるのは傍にいる私にはよくわかった。
なのに……。 悠人の大学進学の話にいつもは誰よりも熱心な夫がその日はまるで心ここにあらずで。 珍しいな。どうしたんだろう。 それが私が夫に違和感を感じた最初だった。
「ねえ、俊太郎くん、話ちゃんと聞いてる?」
私は夕食中の夫に声をかけ、顔をのぞき込んだ。
「ん?あ、何の話だっけ?」
「さっきからずっと話してたのよ。悠人の進路相談のこと。来週の火曜日の午後3時から三者面談があるの。学校に行くのはいつも私だから、たまには俊太郎くんも行ってほしいな。悠人の大学進学について重要な話だし。」
「え?ああ、わかったよ。予定を調整しておく。」
「お願いね。忘れないで。」
「大丈夫だよ、ちゃんと覚えてるから。」
「本当に?」
悠人は建築士になるため、建築学部のある大学を目指していた。
それは義両親や夫にとっても望ましい進路だった。
夫は口には出さないものの、悠人が将来自分の設計事務所を継いでくれることを期待しているのは、私にはよく分かっていた。
でも……。
いつもは悠人の進学の話になると積極的な夫が、その日はまるで気が抜けているようで、違和感を覚えた。
何かがおかしい。
それが、私が夫の変化に気づいた最初の瞬間だった。
夫の帰宅が深夜にずれ込み、私たちはほとんど会話を交わさなくなっていた。 無口な夫。笑顔のない夫。そして家に帰ってこない夫。 どう見ても、夫は私を避けているのが明白だった。 もはや、ただの気のせいとは言えない。 初めて目にするその態度に、私はひどく困惑した。 何があったの?どうしてそんな風に私を遠ざけるの?何に怒っているの?
知り合ってから24年、結婚して20年。 これまで特に大きな問題もなく、深刻なケンカもなかった。 何度考えても、私には思い当たる理由が見つからない。
何かが変わってしまった……。
深夜2時を過ぎた頃、夫がゴルフから帰ってきた。 旅行バッグを抱え、無言でリビングに入ると、朝つけた香水のかすかな匂いが広がった。 夫の顔に笑みはなく、私は「お疲れさま」と声をかけたが、返事はなかった。
これまで朝からゴルフに出かけて、夜中まで帰ってこないことはなかった。夫はどこで何をしていたのだろう? 二階で眠っている子どもたちが起きないこの時間なら、話す機会ではないかと思った。お風呂から出た夫が寝室に来た時、私は声をかけた。
「ちょっと話せる?」
「……何だ?」
夫は無言でベッドに潜り込み、私に背を向けた。
「俊太郎さん、何かあったの?」
「……」
「仕事が大変なのは分かってるけど、最近ずっと話してないし。何かあるなら話してほしいの」
夫は突然振り返り、顔を赤くしながら怒鳴り始めた。
「何もないよ!お前には関係ない!」
「何でそんなに怒ってるの?心配してるだけなんだよ」
「黙れ!お前には関係ないんだ!」
夫は怒りに任せて壁を二度拳で叩いた。その姿に私は息を飲んだ。初めて見る夫の怒りに私はただ震えるだけだった。
夫が部屋を出て行き、私はその場にへたり込んだ。手が震えて止まらない。きっと夫はストレスで一時的におかしくなっているだけだ。すぐに穏やかな彼に戻るはずだと、自分に言い聞かせた。
「おはよう。」
朝、夫がシャツを着ながら階段を降りてくるのを見て、私は声をかけた。昨晩の壁の穴のことには一言も触れなかった。怖くて、どうしても話題にできなかったのだ。
夫が「おはよう」と返してくれれば、まだ私たちは大丈夫かもしれない、そんな淡い期待を抱いていたが、待っても彼からの返事はなかった。
「俊太郎さん、味噌汁いる?」
「…いらない。」
無理に平静を装いながら声をかける私に、彼は短く吐き捨て、洗面所へと向かった。今の彼から感じるのは、私に向けられた怒りと苛立ちだ。会話のたび、彼の言葉が私の心を鋭く刺し、そのたびに胸が痛み、顔が歪んでしまう。
「私、何かした?もしそうなら教えて。もしかして、私の知らないところで何かあったの?」
聞きたいけど、傷つくのが怖くて言葉を飲み込む。
「大丈夫、そのうち元に戻るはず。」と自分に言い聞かせる一方、心の奥底では不安が渦巻いていた。彼が何か隠しているのではないかと疑ってしまう。
夜も眠れず、食事もろくに摂れない。家事も仕事も思うようにできなくなってきた。このままでは、自分を失ってしまいそうで恐ろしい。
「もし私が壊れてしまったら、子どもたちはどうなる?家は?事務所は?代わりの人はいない。私がやるべきことがたくさんあるのに…。」
誰にも相談できず、一人でこの不安を抱えるのは、もう限界だった。
心 療 内 科 へ 行 く
仕事の帰り道、私は初めて小さなメンタルクリニックの扉を開けた。心の中に渦巻く不安の原因は、日々変わり果てていく夫の姿。かつては穏やかだった彼が、まるで別人のようになってしまった。理由もわからず、その変化に怯え続ける日々が続いていた。
その晩、リビングでは何も知らない三人の子どもたちが、いつも通りに夕食を終え、くつろいでいた。
「健二って本当にゲーム下手だよね。そこは違うんだって。ちょっと貸してみなよ、お姉ちゃんがやってあげるから」と長女の美穂が、ゲームに夢中な健二からコントローラーを取り上げた。
「返してよ、自分でできるんだから!お姉ちゃんより僕の方が上手なんだよ!お母さん、美穂が僕のコントローラー取った!」と健一は叫んだ。
「そこ違うよ、ちょっと美穂、貸して。ほら失敗したじゃん。俺ならクリアできたのに、まだまだだな」と、長男の悠人が言った。
「お兄ちゃんが邪魔したからだよ!もう一回やらせて!」と美穂が言い返す。
「お姉ちゃんもお兄ちゃんも邪魔しないでよ!僕がやってたのに!お母さん、ねぇお母さん、二人に言ってよ!」と健二は訴えた。
リビングには、子どもたちの無邪気な声が響き渡る。何も変わらない、いつもの夕食後の光景。兄弟の賑やかなやり取り、それが私の大切な宝物だ。
夫はもともと忙しさを理由に、家庭や子どもたちにほとんど関心を示さなかった。学校行事にもほとんど参加せず、わずか二回しか顔を出したことがない。子どもたちも、朝と夜の少しの時間しか夫と接していないため、夫の変化にはまだ気づいていない。
「宿題終わったの?ゲームもいいけど、早くお風呂入って!」私は少し声を張り上げる。子どもたちにとっては、いつも通りの夜だった。
そして、子どもたちがそれぞれの部屋で深い眠りについた頃、ようやく夫の車がガレージに入る音が聞こえた。
夜も更け、子どもたちが各自の部屋で深い眠りについた頃、ようやく夫の車がガレージに入る音が聞こえた。
「おかえり。ご飯食べる?」と声をかけたが、夫は無言で浴室に向かった。
入浴を終えると、ビールを片手にソファに腰を下ろし、録画していた番組を見始めた。ほんの半年前までは、この時間が唯一の二人だけの時間だった。隣に座りながら、夫と仕事や子どもたちの話、世間話をするのが日課だった。
仕事のストレスもビールと共に薄れて、夫はいつもよりおしゃべりになるのが常だった。夫にとって、私が唯一の話し相手なんだろうと感じていた。あの頃は、それが楽しかった。
だが、今ではその思い出も遠い昔のように感じる。夫はただ、黙ってテレビを見ているだけだった。
「今日ね、帰りに心療内科に行ってきたの」と、私は意を決して口を開いた。こんな話を聞きたいとは思わないだろうことは理解している。でも、もう我慢ができなかった。何も言葉を発しない夫に向かって、私は続けた。
「聞いてる?ごめんね、こんな話。でもちゃんと聞いてほしいの」
返事はなく、夫はテレビを見続けているだけだった。
「ねえ、翔太さん……」私はそのまま床に座り込み、涙をこらえられなかった。
どうして夫は変わってしまったのか。どうして、話し合いもできないのか。元通りの夫婦に戻りたい。子どもたちのために。
泣き崩れる私の横で、突然夫の笑い声が響いた。驚いて顔を上げると、夫はテレビのお笑い番組を見て笑っていた。まるで、私の存在が見えていないかのように。
もう限界だった。このままでは本当に壊れてしまう。私はキッチンに向かい、手に取った白い錠剤を口に入れた。子どもたちにはこんな姿、見せられない。
薬が効いてくると、心の中の不安が嘘のように消えていった。しかし、その代わりに罪悪感が押し寄せてきた。涙がまたこぼれ落ちる。子どもたちの笑顔が頭に浮かんでは消える。
「ごめんね。こんな母親でごめんね」と、心の中で何度も子どもたちに謝り続けた。
リビングからは、夫の笑い声が変わらず響いていた。
夫の浮気を現実認識
庭先のラベンダーがほのかに甘い香りを漂わせる肌寒い5月の夜。激しい雨が降りしきり、息苦しさを感じる。ここ数日、夫の帰りはいつも遅く、今夜も時計の針は12時を過ぎてしまった。
以前、夫は遅い帰宅の理由を「社長たちとの会合だから仕方ない」と言い放った。しかし、年配の社長が連日午前様になるなんて、どう考えても無理な話だ。その言い訳に、私の不安は募るばかり。
この半年、夫が設計事務所に提出した接待費の領収書のほとんどが同じ店の名前「ドルチェ」を記していることが気にかかる。駅前にある高級クラブだ。
「最近、この店によく行くね」と尋ねると、「ああ、そこは社長仲間の集まりだから」と夫は言った。その時は疑いを持たずに「社長たちはお金持ちなんだな」と返したが、夫はそれには答えなかった。
今夜も夫は「ドルチェ」にいるのだろうか。どうしてそんなに頻繁に行くのか。まさか、そこで誰かと会っているのでは?もしかして女性?そんなはずはないと自分に言い聞かせる。
結婚して20年、他の女性に心を移したことのない夫だから、今はストレスを発散しているだけのはず。ホステスもプロだし、無駄な関係は持たないだろう。それでも、なぜ?信じたい気持ちと疑念が心の中で交錯する。
「ねえ、あなたは毎晩どこで何をしているの?そのドルチェには何があるの?」24年間築いてきたものが、この手から零れ落ちてしまいそうで、聞くことができない。夫の暴力が怖いのではなく、夫が私から離れてしまうことが一番恐ろしいのだ。
時計の針が午前二時を過ぎた。今夜も夫は帰らない。振り返ると、20年間にわたってこんなに頻繁に夜帰りが続くことはなかった。いったい夫はどこで何をしているのか。待つことに耐えられず、私は夫の携帯に電話をかけた。
夫が出た。「もしもし、俊太郎さん?今どこにいるの?」それが彼が一番聞きたくない言葉だと分かっていたが、不安で眠れずにいる私にはもう黙って待つことができなかった。「お前には関係ない。俺の勝手だろ。なんで電話してくるんだ?」不機嫌に言い捨てられ、私が何も言えないうちに通話は切れた。
どうしてこんなことになったのか、私が何をしたのか、夫に何があったのか、もう何をどうしたらいいのか分からない。暗い寝室で携帯を握りしめながら、私は激しい動悸と息苦しさに襲われた。呼吸が乱れ、指先が痺れ、汗が額から流れ落ちて、喉が詰まる感覚が襲ってきた。息ができない!?誰か助けて!叫びたいが、寝ている子供たちに気づかれたくない。
父親が深夜に帰ってくることも、母親がこんな状態でいることも、二人の会話がほとんどない関係も。私は急いで安定剤を口に入れ、胸を押さえた。恐怖で思うように息が吸えず、まるで死ぬのではないかという感覚に襲われた。これが私の初めてのパニック障害、過呼吸の発作だった。
もう一度夫に電話をかけたが、彼は出なかった。ベッドに倒れ込み、心の中で助けを呼ぶ。家族もいない私に頼れるのは夫だけ。苦しさに耐えきれず、二錠目の安定剤を口に入れた。薬が効くまでの間、私は怖くて泣いた。子供たちに気づかれないことだけが救いだった。
今、夫の隣にいるのは誰だろう。まさか、女性なんてことはないよね。結局、その夜も夫は朝方まで帰ってこなかった。
夫の飲み友達からの告げ口
今夜もすでに
子供たちはそれぞれの寝室でぐっすり眠っている。私は安定剤を口に入れることでしか心を保てなくなってしまった。かつては抵抗があった薬も、今では私にとってかけがえのない唯一の救いになっている。この薬なしでは、家事も仕事も、正気でいることすらできそうにない。
今夜も夫は「ドルチェ」にいるに違いない。毎晩のように通い詰め、大金を使っている夫は、一体そこで誰と何をしているのだろう。疲労と薬の副作用で朦朧としながら、私は携帯電話を手に取った。かける相手は夫だ。もちろん嫌がられることは分かっているが、もう我慢する余力は残っていなかった。ただ、夫に帰ってきてほしかった。私と子供たちが待つこの家に戻ってきてほしかった。
夫に女ができたなんて、私の思い過ごしだと信じたい。この電話で少しでも希望を得られれば、私は救われる。苦しみから解放されたい。俊太郎さん、お願い、電話に出て。
私は疲れと薬の副作用で頭がぼんやりしていたが、思い切って携帯を手に取った。
かける相手はもちろん夫だ。嫌がられることはわかっているが、もう我慢できる気力が残っていなかった。家に帰ってきてほしい、私と子供たちが待っているこの家に戻ってきてほしい。夫が他の女性と関係を持っているなんて、そんなことは考えたくない。もしこの電話で、少しでも希望が見つかれば、私は救われるかもしれない。この苦しみから解放されたいと願った。
「俊太郎さん、お願い、電話に出て」と呟いた。呼び出し音が四回鳴った後、予想外の声が聞こえた。「あ?もしもし?奥さん?俊太郎くんの奥さんでしょ?」電話の向こうからは知らない男性の声がした。
「…あなた、どなたですか?」と尋ねると、彼は「俺、安藤だけど」と名乗った。安藤は、夫が設計事務所の所長になってから知り合った同業者だった。
「…主人は?主人は居ますか?これ主人の携帯ですよね?」と焦りながら聞くと、「あー健太郎くんは今トイレに行ってるよ」と答えが返ってきた。「そうですか。ではかけ直します」と言った瞬間、彼が「ちょっと待って奥さん!切らないで」と呼び止めた。
「え?なにか……?」と戸惑うと、安藤は言った。「お宅の旦那、不倫してるんだよ。知ってた?不倫だよ、不倫!知らないのは奥さんだけだよ」
「え?不倫?主人がですか?」と信じられない思いで問い返すと、「そうだよ。いつもその女とこの店で会ってるんだよ。俺たちがいても全然おかまいなしでさ、いちゃいちゃが激しくって見てらんないよ」と続けた。
「…そんなはずないです」と否定するが、安藤は「だったらここに来て見たらいいじゃん。奥さん知らないと思ったから教えてあげたんだよ。知らないのは奥さんだけだから気の毒だと思ってさ。ショックだった?いいね?ちゃんと教えたからね。わっはっはっは」と笑った。
その言葉と笑い声が、私の耳に残ったまま携帯は切れた。心の中に広がる恐怖と絶望感に、私はただ呆然と立ち尽くしていた。
社長の笑い声と周囲の楽しげな音が耳に残る中、電話は切れてしまった。夫が不倫している…。全く疑っていなかったと言ったら嘘になるが、それはこの瞬間まで私の想像に過ぎなかった。今日、この言葉を聞くまでは。しかし、私の抱いていた疑念は今夜、現実として目の前に姿を現し、その冷酷な一面を見せつけてきた。頭の中が真っ白になった。
43年間、この小さな田舎町で生きてきて、不倫は都会やテレビの中の出来事だと思っていた。まさか、それが私たち夫婦に起こるなんて。この夜、私は他人から夫の不倫を知らされることになった。できれば夫を信じたい。私たちには、24年間積み重ねてきた絆があり、愛する三人の子供もいるのだから。
社長の言葉が何度も頭を巡る。午前3時、夫が代行車で帰宅した。どうしよう…。なんと言おう…。事実を告げたら、また暴れるかもしれない。それだけは絶対に避けたい。どうしよう…。私の横にある壁に、夫が拳で開けた穴を見つめながら。
玄関の鍵が開く音が聞こえる。夫のスリッパの音が少しずつ近づいてくる。夫が寝室に入ってきた。ベッドに座っている私を見て、夫は明らかに不思議そうな表情を浮かべた。
私が不安を抱えていると、夫が寝室に入ってきた。先ほどの社長の言葉が、もう無視できなくなっていた。
「社長が言ってたんだけど、あなたが不倫してるって…どういうことなの?」
「え?何それ。お前は何を言っているんだ?」
夫は驚いた表情を浮かべている。どうやら、社長から私との電話のことを聞いていないようだ。
「あなたの携帯に電話したら、社長が出てきて、あなたがここで不倫相手と会っていると言ったの。私だけが知らなかったって。これって本当なの?」
「お前、社長と話したのか?なんでそんなことをしたんだ!」
「私は知らないよ。社長が勝手に出たんだから」
「お前が電話してくるからだ!」
「夫婦なのに、なんで電話しちゃいけないの?」
「うるさい!」
「社長は、あなたの不倫を知らない私が可哀想だと言ってた。本当に不倫してるの?」
「そんなことあるわけないだろ!お前は理解できないのか?社長の悪戯だ!酔っ払ってからかってるだけだ!」
「いくら酔ってても、あんなこと言うかしら。私と会ったこともないのに」
「だから、酔ってからかってるんだよ。お前はそんなこともわからないのか!」
「じゃあ、全部嘘ってこと?社長の作り話だって言うの?」
「ああ!そうだよ!もういい加減にしろ!」
夫は不倫を否定した。私が強く出るのに驚いた夫は、慌てて部屋を出て行った。後を追おうとしたが、思いとどまった。
これ以上彼を刺激すると、また暴力が振るわれるかもしれない。父親が母親に暴力を振るうなんて、子供たちが知ったら傷つくだろう。それだけは避けたかった。
私の予想もしなかった反応に戸惑う夫の表情。顔は真っ赤になり、血管が浮き上がっている。彼がこんな顔を見せるのは珍しい。あれは、彼が嘘をつくときの表情だ。
「俺がそんなことするわけないだろ。お前は馬鹿だな。冗談を真に受けるな。社長には俺からちゃんと文句を言うから。俺を信じろ。大丈夫だから。心配するな」と言ってくれたら、どれほどよかっただろう。
しかし、現実は違う。
ベッドの横にあるサイドテーブルには、結婚式の写真が飾ってある。私にとって、これが本当の夫だ。今の彼は所長のストレスで、ただ少しおかしくなっているだけ。きっと、また元の二人に戻れるはず。
私は、こんなことがあっても、まだ夫を信じる気持ちを完全には捨てられない。20年前、私が生涯の伴侶に選んだ人だから。この世でたった一人、私の大切な三人の子供の父だから。この20年、信じて共に生きてきた人なのだから。そして、私はまだ彼を愛しているから。
私が動揺していると
夫が寝室に入ってきた。さっきの小山社長の話が頭から離れない。「小山社長が言ってたよ。あなたが不倫してるって…。どういうことなの?」
「は?なんだそれ。何を言ってるんだ?」
夫は驚いた様子で、私との電話のことを知らないようだった。「さっきあなたの携帯に電話したの。小山社長が出て、あなたがここで不倫相手と会ってるって言ったの。私だけが知らなかったみたい。どういうこと?」
「お前、小山社長と話したのか?なんでそんなことをするんだ?」
「知らないわよ。小山社長が勝手に出たのよ。」
「お前が電話してくるから悪いんだ!」
「夫婦なのに電話してはいけないの?」
「うるさい!」
「あなたの不倫を知らないのは私だけで気の毒だって。小山社長が言ったこと、本当なの?」
「そんなわけないだろう!それは小山社長の冗談だ!酔っ払ってふざけただけに決まってる!」
「酔っ払ってたからって、そんなこと言うかしら?」
「だからお前をからかって楽しんでるんだよ!酔っ払った上での冗談!」
「全部嘘ってこと?」
「ああ、そうだよ!もうやめてくれ!」
夫は不倫を否定した。私が珍しく食い下がると、驚いた様子で部屋を出て行った。後を追おうとしたが、止めた。これ以上興奮させると、また暴力を振るうかもしれないから。
父親が母親に暴力を振るう姿を子供たちに見られたら、傷つくだろう。それだけは避けたい。
夫の動揺した顔が思い浮かぶ。真っ赤になり、額に血管が浮き出ていた。めったに見せない顔。これは夫が嘘を言うときの表情だ。
「そんなことするわけないだろう。お前は馬鹿だな。冗談に決まってる。小山社長には文句を言っとくから。信じてくれ、大丈夫だから。」
夫がそう言ってくれたらよかったのに。しかし、現実は違う。
ベッドの横のサイドテーブルにある写真立てには、結婚式の写真が飾られている。私にとって、これが本当の夫だ。今の夫は所長になったストレスで、ちょっとおかしくなっているだけだ。きっと、またあの頃に戻れるはず。
私はまだ夫を信じたい気持ちを完全には捨てきれない。20年前に生涯の伴侶として選んだ人だから。この世にたった一人、私の大事な3人の子供たちの父だから。20年、共に信じて生きてきた人だから。そして、私はまだ夫を愛しているから。
義母への告白決断
「香織さん、税理士の佐藤先生から電話です。」
いつも通り設計事務所で忙しくしている私が、社員から電話の子機を受け取った。
「はい、香織です。佐藤先生、いつもお世話になっております。」
「香織さん、帳簿を見せてもらったよ。今日は接待交際費の件で連絡したんだ。」
「…何か問題がありましたか?」
「特定のお店にかなりのお金を使っているようだけど、これには注意が必要だね。貴社の事務所としてはかなりの高額だし、連日続いているのも気になる。最近の接待交際費は昨年度の5倍になっているよ。香織さん、何か事情があるのかな?」
「いえ、それについては私からお答えできません。申し訳ありませんが、今後十分に気をつけます。」
「そうしてもらわないと、少々困ります。私が言ったことを所長に伝えておいてください。お願いします。」
「はい、わざわざありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。」
電話の相手に私は頭を下げた。
夫がドルチェに落とす金額は、月に40万円を超えていた。もちろん、小さな設計事務所の接待交際費としては異常な額だ。
夫はその話題に触れると、すぐに怒ってしまうため、会話ができない。先生からの伝言を伝えたところで、今の夫は私の言葉を聞いてくれないだろう。しかし、このまま放置するわけにはいかない。早急に対処しなければ。
焦る私は、思い切って義母に相談することに決めた。接待交際費のことだけでなく、最近の夫の言動についても話すつもりだ。義母を選んだのには理由があった。
退社後、誰もいない公園の駐車場に車を停めた。
「はい、田中ですが。」
受話器の向こうから、いつも通り穏やかで優しい義母の声が聞こえた。義母は若い頃から義父の不貞に苦しんできたと、私は夫から聞かされていた。だからこそ、夫について相談するのには義母が一番適していると感じた。